公的年金等からの個人住民税の特別徴収(年金特徴)について
更新日:2025年10月27日
年金特徴とは
公的年金等受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を目的として公的年金から市民税・県民税(個人住民税)を引き落としするものです。
金融機関へ足を運ぶ手間を省くことができるほか、普通徴収では4回だった納期が年金支給月の6回になることで1回あたりの負担が軽くなります。
対象となる人
4月1日時点で65歳以上の年金受給者で、前年中の公的所得から計算した個人住民税が課税されているかた。
ただし、次のいずれかに該当する場合は特別徴収の対象となりません。
- 公的年金等のうち、国民年金法に基づく老齢等年金給付等((注釈1)、以下「老齢等年金」という)の給付額が年間18万円未満の場合
- 所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、個人住民税の特別徴収税額の合計額が老齢等年金給付等より多くなる場合(注釈2)
- 介護保険料が老齢等年金給付等から特別徴収されていない場合(注釈3)
- (注釈1)老齢等年金給付等とは、国民年金法による老齢基礎年金その他の同法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法または私立学校教職員共済組合法に基づく老齢または退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの、およびこれらの年金たる給付に類する老齢または退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものをいいます。
なお、この老齢等年金給付等には、遺族年金、障害年金等の非課税年金は含まれません。 - (注釈2)企業年金等を含めた公的年金等の支払額が多い場合でも、老齢等年金給付等を基準に判定されます。
- (注釈3)平成25年度税制改正により、4月1日において介護保険料の特別徴収対象被保険者であれば、それ以降に介護保険料の特別徴収が停止されたとしても、一定の要件の下、個人住民税の特別徴収の対象となることとされました。
年金特徴される税金
公的年金から特別徴収される税額は年金所得から計算した税額のみとなります。給与所得、事業所得など、公的年金以外の所得に係る税額は、これまでどおり給与からの引き落とし、または納付書で納めていただくこととなります。
年金特徴が停止となる場合
次のような事由が生じた場合は、年金特徴が停止になります。停止になった場合、特別徴収できなくなった税額は、ご本人様に納めていただく普通徴収(ご本人で納付する方法)となりますので、市からあらためて、納税通知書を送付します。
- 当該年度の4月1日において、鎌ケ谷市の介護保険の特別徴収対象被保険者でなくなった場合
- 鎌ケ谷市を転出した場合(10月1日から12月31日までに転出された場合は停止されません。当該年度の1月1日から3月31日までに転出された場合、翌年度10月の特別徴収から停止されます)
- 公的年金から特別徴収されているかたが死亡した場合
- 12月11日以降、年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額が変更となったときなど
年金特徴による個人住民税の徴収方法
【例 前年度が年金特徴でないかたが今年度から年金特徴となる場合、今年度と次年度の年金特徴税額は次のようになります。(鎌ケ谷市の場合)】
年税額の半分を普通徴収で1期と2期で納めていただき、10月から年金特徴となります。
(今年度)年金所得で計算した個人住民税が60,000円の場合
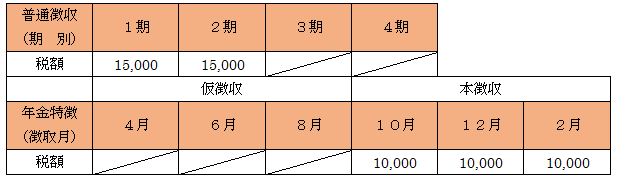
[計算方法]
- (1)年税額の半分を普通徴収とします。
年税額60,000円÷(わる)2=(いこーる)30,000円
普通徴収税額30,000円(a)、年金特徴税額で30,000円(b)
- (2)普通徴収とした額を1期と2期に分けます。
普通徴収税税額30,000円(a)÷(わる)2回=(いこーる)15,000円
1期15,000円、2期15,000円
- (3)年金特徴とした額を10月、12月、2月に分けます。
年金特徴税額30,000円(b)÷(わる)3回=(いこーる)10,000円
10月10,000円、12月10,000円、2月10,000円
(次年度)年金所得で計算した個人住民税が45,000円の場合
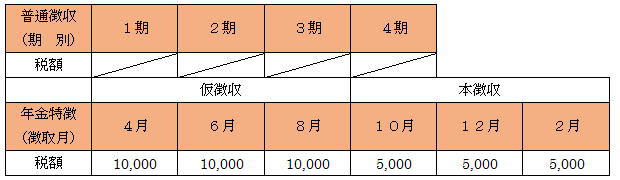
[計算方法]
- (1)仮徴収税額は、前年度分の年金所得による年税額を2で割り、さらに4月、6月、8月に振り分けます。
(前年度の年税額60,000円÷(わる)2)÷(わる)3回=(いこーる)10,000円
4月10,000円、6月10,000円、8月10,000円
- (2)本徴収税額は、今年度分の年金所得による年税額から仮徴収税額を差し引き、10月、12月、2月に振り分けます。
(今年度分の年金所得による年税額45,000円-(ひく)仮徴収税額(4から6月分の合計)30,000円)÷(わる)3回=(いこーる)5,000円
10月5,000円、12月5,000円、2月5,000円
よくある質問
質問1 年金と給与両方から住民税が天引きされています。2重に徴収されていませんか
【回答】給与から天引きされているのは、年金以外の所得に係る税金です。それぞれの所得で分けて納付していただいているものであり、2重に徴収しているものではありません。
質問2 65歳となり、住民税が年金から天引きされるようになりました。もう自分で支払う必要はありませんか
【回答】一度年金からの天引きが開始されても、停止される場合があります。その場合には、普通徴収(納付書又は口座振替)で納付していただくこととなります。市から送付される税額決定(変更)納税通知書は必ずご確認ください。
質問3 公的年金からの天引きではなく,従来どおり普通徴収で納付することはできますか
【回答】4月1日時点で65歳以上の人の年金所得に対する税額については、本人の希望で納付方法を選択することはできません。また、これまで給与天引きで住民税を納付いただいていた人についても、4月1日時点で65歳となる人は、年金所得に係る住民税を給与から天引きすることはできなくなります。
質問4 日本年金機構から送られてくる年金の支払通知書の個人住民税の額と、市から送られてくる市民税・県民税税額決定通知書の年金特徴税額が違いますが、別の税金ですか
【回答】市民税・県民税を合わせて個人住民税といい、同じ税金を指しています。日本年金機構からの通知は、市から日本年金機構へ連絡している税額がもとになっていますが、連絡のタイミングにより市からの通知額と異なる場合があります。税額については、市からの通知が正しい税額となります。
質問5 年金の支給額が変わらないのに10月の年金天引き額が8月の年金天引き額より増額しています。誤りではないですか
【回答】まず、住民税は、前年中の所得を基に計算し、6月に税額が決定されます。しかし、年金特徴の場合には、税額決定前の4月から既に徴収を開始しており、天引き額については、仮徴収として前年度の年金所得に係る住民税額を概ね6分の1にした金額としています。そして、6月に年税額が決定されたのち、確定した年税額から仮徴収の金額を差し引いた金額を、本徴収として10月、12月、翌年2月の3回に分けて天引きします。
そのため、その年の年金から天引きする税額が前年度の税額より多い場合などには、10月からの天引きの額が増えることがあります。また、反対に前年度より少ない場合などには、10月から少なくなることがあります。
質問6 6月に税額通知書が届きましたが、6月支給の年金から天引きされている住民税が税額通知書よりも多く徴収されています。差額は還付になるのですか
【回答】4月、6月、8月の年金からそれぞれ天引きされる住民税額は、前年度の年金所得に係る住民税額を概ね6分の1にした金額であり、前年度において決定された仮徴収税額となります。そのため、6月に決定される今年度の住民税の年税額が既に徴収済みの仮徴収税額を下回る場合には、後日、差額が還付されることとなります。
問い合わせ
総務企画部 課税課 市民税係


