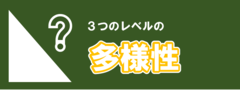生物多様性があぶない!
更新日:2023年5月1日
地球上のすべての生命を支えている生物多様性(せいぶつたようせい)が、これまでにない速さで失われつつあり、多くの生物が絶滅(ぜつめつ)の危機(きき)に瀕(ひん)しています。
原因はさまざまですが、そのほとんどが人間活動によるものです。
4つの原因
1.開発(かいはつ)・乱獲(らんかく)

わたしたち人間が道路や住宅などをつくるために、木を切ったり水辺を埋(う)めたりすることで、生き物のすみかを奪(うば)ってしまいます。
また、道路やダムなど、人間が構造物(こうぞうぶつ)を設けたことで生息できる範囲(はんい)が狭(せま)くなることや、生物の移動を妨(さまた)げることでエサ不足になったり、近親交配(きんしんこうはい)で種内における遺伝子(いでんし)の多様性(たようせい)を損なってしまいます。そして、食料や観賞用(かんしょうよう)、ファッションなど、人間の贅沢(ぜいたく)のために動植物が過剰(かじょう)に採取(さいしゅ)されているという現状も生態系(せいたいけい)に大きな影響(えいきょう)を与えています。
2.里山里地の手入れ不足

里山里地に入らなくても、スーパーや通販(つうはん)などで色々なものを手軽に入手できるようになったり、少子高齢化(しょうしこうれいか)や地方の過疎化(かそか)により、里山里地を手入れする人手が不足するようになりました。その結果、人間が手を加えなくなった里地里山は荒(あ)れてしまい、そこをすみかとする生き物が減ってしまいます。
また、イノシシやシカなどが増えすぎて、木や自然を壊(こわ)し、ほかの生き物のすみかを奪(うば)ってしまいます。
3.外来種(がいらいしゅ)の持ち込み

外来種(がいらいしゅ)とは、もともとその地域にいなかったのに人間の活動によって他の地域から入ってきた生物のことです。
外来種(がいらいしゅ)が及ぼす影響(えいきょう)
・生態系(せいたいけい)への影響(えいきょう)(在来種(ざいらいしゅ)を捕食(ほしょく)して数を減らしたり、絶滅(ぜつめつ)に追いやる。)
・人の生命・身体への被害(毒(どく)をもっている外来種(がいらいしゅ)にかまれたり、刺(さ)されたりする危険。)
・農林水産業(のうりんすいさんぎょう)への被害(農産物(のうさんぶつ)を食べたり、畑を踏(ふ)み荒らす。)
鎌ケ谷市でも、外来種(がいらいしゅ)が発見されています!「注意すべき外来生物」
4.地球温暖化(ちきゅうおんだんか)
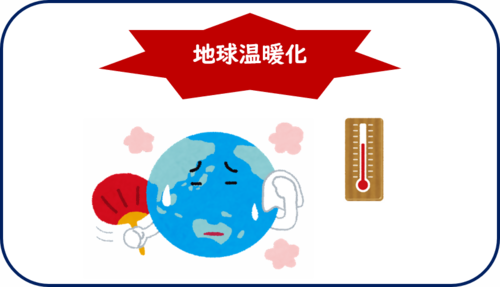
地球温暖化(ちきゅうおんだんか)が進むと、氷が溶けだす時期が早まったり、海面が上昇したり、様々な変化が現れます。近年、日本においても、連日の 猛暑日(もうしょび)、災害級の 豪雨(ごうう)の増加、桜や紅葉の時期がずれ込んでいるなど、 地球温暖化(ちきゅうおんだんか)が原因と考えられる変化を感じることが多くなりました。環境が変われば、生物たちは生息しづらくなり、自分たちにあう場所を探して移動します。また、環境の変化についていけない生物や、移動が困難な生物は、 絶滅(ぜつめつ)してしまう可能性もあるのです。地球の平均気温が1.5度から2.5度上昇すると、動植物の 絶滅(ぜつめつ)のリスクは20%から30%高まると言われています。
「生物多様性ってなあに?」その他リンク
問い合わせ
市民生活部 環境課 温暖化対策推進係